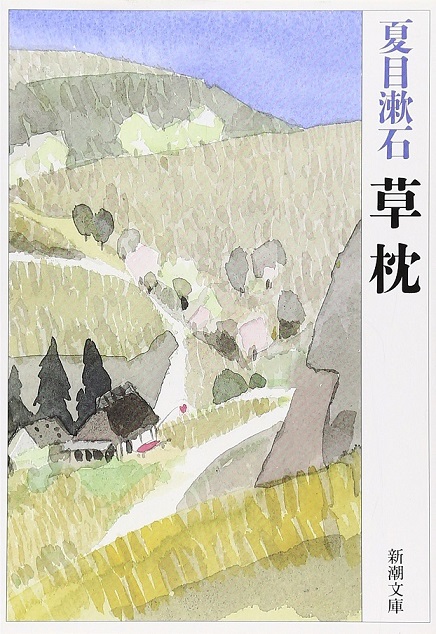明治39年(1906年)、夏目漱石39歳。
この3作は漱石の初期の代表的な作品といわれている。
「草枕」は、熊本のとある温泉場に逗留している若き画工(画家)の、一人称で語られる小説である。
山路を登りながら、こう考えた。
智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。
兎角に人の世は住みにくい。
初めて全篇読破した私は、最初は注解を頼りに読んでいたが、中盤以降は、少々意味が分からなくてもそのまま読み進めていった。
柄谷の解説は「草枕」に特化したもので、読後に読んでなるほどなるほどとうなる。漢語のように難解な表現に引っかからずに前へ進む、私のいい加減な読み方も、柄谷の解説によると、一理有るのだと、自らの教養のなさを慰める。
「草枕」は、たとえて言うと、緩やかな川を下る船に乗ったような小説である。特段ストーリーもなく、船から見える移り変わる景色を、リズム感のよい文体で語ってくれるような小説である。
ときどき、白い優美な水鳥が行きかうが、それが魅力的な女性、那美(なみ)である。また、のんびりと甲羅干しをする亀もいる。それが、山寺の住職である。
画工がひとりで温泉に浸かっていると、同じ浴槽に那美さんが入ってくるシーンが有る。おそらくこの小説を読んだ人は、ここのシーンだけは覚えているだろうと思われる。漱石の、印象的な発想と描写で際立つ場面なのである。
そんなドキドキするような出来事も、早瀬で少しスリリングだっただけで、また何もなかったようにとろ場を行く船のように、小説は音もなく展開していく。
「しかし若いうちは随分御読みなすったろう」余は一本道で押し合うのをやめにして、ちょっと裏へ廻った。
「今でも若いつもりですよ。可哀想(かわいそう)に」放した鷹(たか)はまたそれかかる。すこしも油断がならん。
「そんな事が男の前で云えれば、もう年寄のうちですよ」と、やっと引き戻した。
「そう云うあなたも随分の御年じゃあ、ありませんか。そんなに年をとっても、やっぱり、惚(ほ)れたの、腫(は)れたの、にきびが出来たのってえ事が面白いんですか」
「ええ、面白いんです、死ぬまで面白いんです」
「おやそう。それだから画工(えかき)なんぞになれるんですね」
「全くです。画工だから、小説なんか初からしまいまで読む必要はないんです。けれども、どこを読んでも面白いのです。あなたと話をするのも面白い。ここへ逗留(とうりゅう)しているうちは毎日話をしたいくらいです。何ならあなたに惚れ込んでもいい。そうなるとなお面白い。しかしいくら惚れてもあなたと夫婦になる必要はないんです。惚れて夫婦になる必要があるうちは、小説を初からしまいまで読む必要があるんです」
「すると不人情(ふにんじょう)な惚れ方をするのが画工なんですね」
「不人情じゃありません。非人情な惚れ方をするんです。小説も非人情で読むから、筋なんかどうでもいいんです。こうして、御籤(おみくじ)を引くように、ぱっと開(あ)けて、開いた所を、漫然と読んでるのが面白いんです」