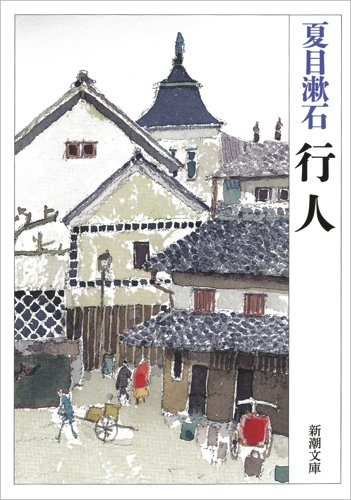
夏目漱石の「行人」。
朝日新聞に「行人」の連載が開始されたのが1912年なので、105年前の小説であるが数十万年の人類の歴史の長さから推し測れば、105年くらいで人の心は変わるものではない。
十代で読んだ「こころ」からすでに約半世紀、「彼岸過迄」 「行人」「こころ」の三部作を、一生涯をかけて読了した。
「行人」には悩める悲しい主人公長野一郎と、一つ家に暮らすその家族、妻の直、弟の二郎、妹のお重、そして両親の精神風景が描かれている。
長野家と長野家を支えるお手伝いさんや、大阪に住む遠縁の元書生、それに、二郎の友人の三沢や、一郎の友人の”H”など、登場人物は漱石の創作した人物だが、実際のモデルがいたことは、漱石自身のエッセイにも明らかなようである。
とりわけ、一郎や二郎や三沢やHは、漱石の分身でもあると思われる。
漱石の職業体験や災害遭遇や入院体験や非日常な会食体験が、この作品にちりばめられている。
何よりも、悩める悲しい孤独な一郎は、漱石の分身ではなかろうかと想像される。妻の直とのつらい関係に沈み、弟の二郎と妻の関係を疑り、ガラスのような壊れやすい神経を持った、しかし、才能のかたまりのような知識人でもある。
一郎とは対照的に、弟妹の二郎と重、妻の直、長野家の当主夫婦(兄弟の両親)などは、実に自由人で、天心爛漫に描かれている。これも実は漱石の分身なのだろう。
二郎のたっての願いで、Hは一郎をつれて旅に出る。タイトルの旅人という意味の「行人」は、この旅から命名されているのか、あるいは人生を「旅」ととらえているのか。いずれにせよ、その旅先から二郎に所望されて、旅先の兄の様子がHから送られてくる。
最終章は、原稿用紙100枚にも及ぶ、Hの手紙で終始する。
そして、悩める一郎を観察し解析し問いかけをするHも、取りも直さず漱石自信なのである。
このHからの手紙は「こころ」の先生の手紙(200枚)とともにつとに有名なのだそうである。漱石が胃潰瘍を煩いながら、一郎とHになりきって渾身の思いを、100枚に綴っている。後世に遺すことをはっきりと意識した、漱石の哲学書、宗教書のようでもある。
私なら、山が動かないなら、幸福のために山のほうへ歩いていく。
何を犠牲にしても、山が動くことを待つ神の様な人には到底及ばない。でもそれでいい。
以下、Hの手紙一部分。(二郎宛のため、一郎のことは「兄さん」とされている。)
「何故山の方へ歩いて行かない」
私が兄さんにこう云っても、兄さんは黙っています。私は兄さんに私の主意が徹しないのを恐れて、附け足しました。
「君は山を呼び寄せる男だ。呼び寄せて来ないと怒る男だ。地団太を踏んで口惜しがる男だ。そうして山を悪く批判する事だけを考える男だ。何故山の方へ歩いて行かない」
「もし向うが此方へ来るべき義務があったらどうだ」と兄さんが云います。
「向うに義務があろうとあるまいと、此方に必要があれば此方で行くだけの事だ」と私が答えます。
「義務のないところに必要のある筈がない」と兄さんが主張します。
「じゃ幸福の為に行くさ。必要のために行きたくないなら」と私が又堪えます。
兄さんはこれで又黙りました。私のいう意味はよく兄さんに解っているのです。けれども是非、善悪、美醜の区別に於て、自分の今日までに養い上げた高い標準を、生活の中心としなければ生きていられない兄さんは、さらりとそれを擲って、幸福を求める気になれないのです。寧ろそれに振ら下がりながら、幸福を得ようと焦燥るのです。そうしてその矛盾も兄さんには能く呑み込めているのです。
「自分を生活の心棒と思わないで、綺麗に投げ出したら、もっと楽になれるよ」と私が又兄さんに云いました。
「じゃ何を心棒にして生きて行くんだ」と兄さんが聞きました。
「神さ」と私が答えました。
「神とは何だ」と兄さんが又聞きました。