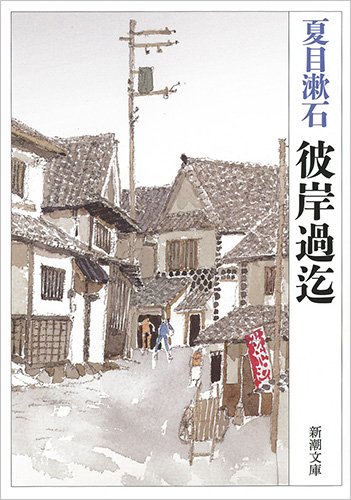
試験の問題としては、いささか長い文章だったが、紛れもない漱石の文体で、印象に残った文章であった。この作品、まだ未読だった私は全編を読んでみることを決心。
登場人物たちは、知識人で裕福であり、明治45年ですでに、親戚間の連絡を自宅の電話を使うほど裕福な層である。ただ彼らがどんな仕事をしているのかまったく分らない。
物語の前半は、無職と思しき男たちのゲームのような暮らしと、生活感溢れる現実的な女たちを、対照的に観察日誌のように描写する。
高等教育を受けたにもかかわらず、親の遺産があり、役人でもなく会社勤めをするでもなく、まったりと暮らす須永が主人公。
後半、そんな「高等遊民」の須永と、千代子の結婚話の進展と、二人の間に現れた高木への須永の嫉妬、これが物語の核となっている。
英国留学帰りで屈託のない爽やかな好青年と須永の目に映る高木と、鎌倉ではじめて出会うシーンが、センター試験に出題された以下の部分である。
《 二人の容貌が既に意地の好くない対照を与えた。然し様子とか対応振とかになると僕は更に甚しい相違を自覚しない訳に行かなかった。僕の前にいるものは、母とか叔母とか従妹とか、皆親しみの深い血族ばかりであるのに、それ等に取り捲かれている僕が、この高木に比べると、却って何処からか客にでも来たように見えた位、彼は自由に遠慮なく、しかも或程度の品格を落す危険なしに己を取扱かう術を心得ていたのである。知らない人を恐れる僕に云わせると、この男は生れるや否や交際場裏に棄てられて、そのまま今日まで同じ所で人と成ったのだと評したかった。彼は十分と経たないうちに、凡ての会話を僕の手から奪った。そうしてそれを悉(ことごと)く一身に集めてしまった。》
幼馴染の千代子との結婚話には冷淡で、千代子の愛を感じながらも、結婚に踏み切れない内向的な須永。しかし、千代子と高木の仲を悶々と詮索し、想像し、自分の中に閉じこもる。
千代子はどんな人とも虚飾なく等間隔で接することのできる、姿も内面も生来の魅力を持った女性に漱石は描いている。たしかに、胸騒ぎがするほど魅力的である。
上に紹介した「須永の話」と題されたこの章は、須永の淡々とした独白部分である。静かな描写にもかかわらず、千代子と須永の狂おしい情念の交わりと、
激しく悲しい会話のやり取りに終始圧倒される。
須永は漱石自身だと言う説がある、明治のエリートの悲しみがここに在る。大病を克服して生還し、みなぎる生命力も感じ取れる。
静かな年末年始にぜひ読まれたい1冊である。