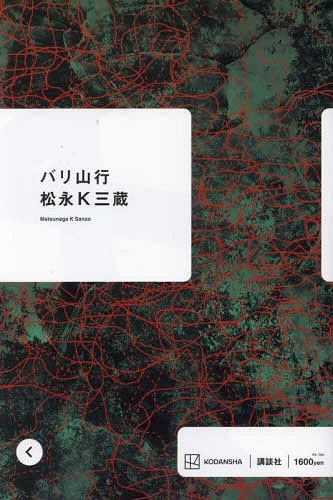
1年前の芥川賞受賞作、松永K三蔵の「バリ山行」を読みました。
バリ山行とは、地図で示されたメジャーな登山路を避けて、バリエーションのある独自のルートで山登りすることで、例え低山でも初心者には危険をともなう山行になる。
私も若い頃、3人で京都市内の低山に登った後、通常ルートを避けて下山する途中で道に迷ったことがある。2時間は迷っただろうか、日没までは時間があったのと天気がよかったことが幸いして、どこかの民家の建つ場所に出られて事なきを得た経験がある。あの恐怖は、ちょっとしたもので、50年前のことだが今でも忘れることができない。
本作の舞台は六甲山系のすそ野の街。阪神間に長く拡がる街には3社の電車が並行して走り、どこの駅からでもバリエーション山行が楽しめる。
著者は本作のモデルになったような建築関係の会社で働きながら、小説を書いて山行も楽しんできた半生だったようで、それだけで人生「竣工」している気もする。
主人公波多(はた)は、会社の同僚たちとの付き合いで始めた山登り初心者だが、妻鹿(めが)という先輩が独りでバリ山行をしていることを知り、興味を持ち始める。
妻鹿は登山用アプリの地図に自分の山行のルート地図の記録を残していて、第3者も共有できる。(そんな楽しみ方があるんだと知る、私) 波多は本人に内緒でそれを毎週トレースしていて、見るだけでなくバリ山行に参加したいと強く思うようになるのだった。
妻鹿と波多の2人によるバリ山行は迫力がありスリリング。本作後半での、波多の単独の山行も力強い描写で惹かれる。歩きながら内面を見つめる内省的な描写が秀逸で、六甲の大自然の自然の情景と相まって、美しく生々しい力強い描写となっている。
「人生も仕事も、バリ山行みたいに紋切り型でないところが楽しくて面白いのよ」といったテーマの小説だと容易に想像できるというか期待していたが、そんなに簡単なことでもなくて...という感じが悪くない(どっちやねん)。本流と亜流を行ったり来たりの人生と仕事もすこぶる面白いこともあるし...。
純文山岳小説という出版社による謳い文句が付けられているが、そんな括りも適当ではない気がする。
昨今の芥川賞の、読み手が見放されるほどの突き放し感はなくて、物語の輪郭もくっきりとしている「健康にやさしい」純文学だ。
最後の最後に...。
実際のバリ山行はお勧めできないが、本書はおすすめ度◎、ぜひ手に取られたい。
【あらすじ】
古くなった建外装修繕を専門とする新田テック建装に、内装リフォーム会社から転職して2年。会社の付き合いを極力避けてきた波多は同僚に誘われるまま六甲山登山に参加する。その後、社内登山グループは正式な登山部となり、波多も親睦を図る目的の気楽な活動をするようになっていたが、職人気質で変人扱いされ孤立しているベテラン社員妻鹿があえて登山路を外れる難易度の高い登山「バリ山行」をしていることを知ると……。
会社も人生も山あり谷あり、バリの達人と危険な道行き。圧倒的生の実感を求め、山と人生を重ねて瞑走する純文山岳小説。