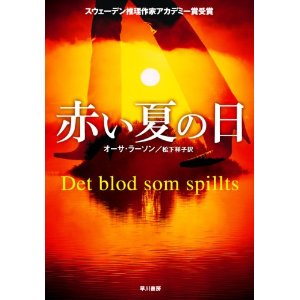
赤い夏の日 オーサ・ラーソン 松下祥子 (訳) (ハヤカワ・ミステリ文庫)
内容紹介
【スウェーデン推理作家アカデミー最優秀長篇賞受賞】
悲惨な事件に巻込まれ、心に傷を負ったままのレベッカは、職務に復帰した法律事務所で空虚な日々を送っていた。そんな彼女が、上司の出張に同行して故郷のキールナへ戻ってきた。だがそこで待っていたのは、またしても殺人事件だった。教会の女性司祭が夏至の夜に惨殺されたのだ。ふとしたことから被害者の周囲の人々と関わることになったレベッカは否応なしに事件の渦中へ……
第1弾「オーロラの向こう側」を読んだ後、他のスウェーデンのミステリー小説、ヴァーランダーシリーズやミレニアムシリーズなどを読んでいたら、もう4年の月日が経ってしまった。
作者は女性なので、今作も物語の中心をなすのは女性陣。
物語の核となるのが、女性司祭ミルドレッド。魅力的な聖職者でありフェミニストであり、協会の所有する森に棲む雌狼の命までも守ろうとするセンス・オブ・ワンダーの持ち主でもある。彼女に周りには、当然に女性たちが吸い寄せられるように集まってきて、女性だけの聖書研究会のようなものができる。
物語の冒頭に司祭ミルドレッドの死体が教会で発見される。したがって、生存中の生身の司祭は物語には登場しない。しかし、三人称で書かれた本書では、彼女に関係した人たちの心のなかの回想シーンで、司祭の言葉や面影や行動や考え方がいきいきと立ちあがってくる。
司祭の殺人事件の捜査にあたるのが、女性警部アンナ。彼女は前作にも登場したが、途中で産休に入ってしまった。今回は産休明けで、部下の男性警官たちと丹念な捜査を進めていく。
そして、前作での心の傷がいえないままのレベッカは、故郷で再び殺人事件に巻き込まれてしまう。本作では他の女性たちと同じ程度の登場時間であるが、レベッカの登場するシーンは、司祭の登場シーンと対照的で現実的であり、物語のもう一つの核となっている。
レベッカは、幼いころに森で暮らした自身の生活をその故郷で追体験し、傷ついた心を癒そうとする。タイトなスーツをジャージに着替えて森の苔の上で大の字になり、フラッシュバックしてくる貧しくても幸せだった子ども時代に思いを馳せる。また、偶然知り合う大男の知的障害のある青年の純粋さに、人嫌いになった心を揉みほぐされていくのである。
殺された司祭は、女性たちからは天使や母や姉のように慕われていた。しかし、司祭の周辺の男や慕ってくる女性たちの周辺の男たちからは、蛇蝎のごとく嫌われ呪われる存在であった。女が司祭になること自体が男たちには考えられないことなのかもしれない。私も、はじめのうち、この司祭は男だと思っていた。
女が人として自然に生きていくには、この作品を読まなくても大変な障壁があることは理解できる。ことに周辺にいる男の影響は、計り知れなく大きい。男にも同じく障壁は現れるのだが、それを乗り越える力の差は歴然としている、女の足元にも及ばない。
まぎれもないその事実を、作者のラーソンは登場人物たちに投影する。アメリカ西海岸が舞台の探偵小説のような、創られたマッチョなヒーローは登場しない。ラーソンが蛇蝎のごとく男たちを嫌っているのではなく、マッチョに生きたくてもそれを可能にできない男たちを等身大に描いているだけなのだろう。
ただ、タフな女性人たちの中でレベッカだけは、心の傷が癒えるまもなくさらに大きな渦に巻き込まれる。もちろんのこと、司祭殺しの犯人はアンナたちの手によって挙げられるが、レベッカの立ち直る姿は、次作以降に持ち越しとなる。
次はどこが舞台となるのか、お楽しみである。