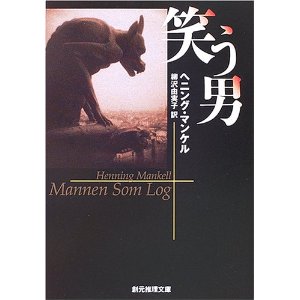
笑う男 ヘニング・マンケル 柳沢 由美子(訳) (創元推理文庫)
お行儀の良い私は、"クルト・ヴァランダー"シリーズを第1作目からこつこつと読んできて、「笑う男」は数えて第四作目にあたる。
もう今度こそ刑事を辞めようと思っていた精神的に落ち込んでいたヴァランダーのもとに、顔なじみの弁護士が訪ねてくる。
弁護士の父親も弁護士で、父親は自動車事故で亡くなったばかりなのだが、「父は不審死だと思う。調べてはもらえないだろうか」と、ヴァァランダーに助けを求めてくる。
ヴァアランダーは、もう刑事を辞めようと思っているから、力になれないと、弁護士の依頼を断る。すると、それから幾日もたたずに、その弁護士は、自分のオフィスで何者かに銃撃され命を落とす。
弁護士の父親も弁護士で、父親は自動車事故で亡くなったばかりなのだが、「父は不審死だと思う。調べてはもらえないだろうか」と、ヴァァランダーに助けを求めてくる。
ヴァアランダーは、もう刑事を辞めようと思っているから、力になれないと、弁護士の依頼を断る。すると、それから幾日もたたずに、その弁護士は、自分のオフィスで何者かに銃撃され命を落とす。
父親弁護士の自動車事故死はともかくも、息子弁護士の死は紛れもない殺人事件である。ヴァランダーは、心と体にムチ打ち、仕事に復帰し、この親子の死の捜査の指揮をとることになる。
捜査を続けていくうちに、父親弁護士の最後のクライアントが捜査線上に上がってくる。そのクライアントは、スウェーデンの大企業の代表で、大きな寄付を多方面で繰り返す慈善家で、ヴァランダーの職場の近くの広大な城に居を構えるビッグな存在である。
今回から、産休明けの若い婦人警官が登場するのだが、女で大学出で若くて優秀な警官に対して、たたき上げの刑事たちの反応は冷たい。唯一、ヴァランダーだけは、彼女の実力を認めてやり、二人は協力して巨悪に挑んでいく。
タイトルの「笑う男」とは、城に住むビッグな実業家のことで、完璧な笑顔の裏にどんな秘密が隠されているのか。一点の曇りもないようなビッグが怪しいとなると、読み手としても俄然、モチベーションが上がってくる。
それにしても、このシリーズはいつもショッキングな犯罪者が登場するのだが、それらがリアルなところが、社会派小説家ヘニング・マンケルのすごいところ。ジェイムズ・エルロイ描くところの、アメリカの実在のギャングより、マンケルの描く北欧の架空の実業家の方がリアルなところが、なんともすごいのである。