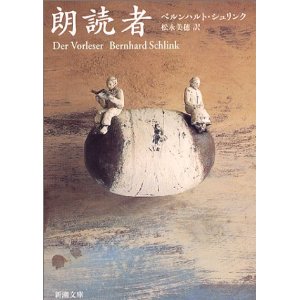
15歳のぼくは、母親といってもおかしくないほど年上の女性と恋に落ちた。「なにか朗読してよ、坊や!」―ハンナは、なぜかいつも本を朗読して聞かせて欲しいと求める。人知れず逢瀬を重ねる二人。だが、ハンナは突然失踪してしまう。彼女の隠していた秘密とは何か。二人の愛に、終わったはずの戦争が影を落していた。現代ドイツ文学の旗手による、世界中を感動させた大ベストセラー。
このように書かれている裏表紙の梗概さえ読まずに、私はいつも小説を読みはじめる。
少し読み進めて、これはどこの国の物語なのだろうと、
作者の経歴に目を留めて、ドイツの作家なのだとはじめて認識。
中学1年の頃、生まれてはじめて自分で購入した文庫本は、
価格100円のへルマン・ヘッセ「車輪の下」だった。
ドイツの小説を読むなんて、それ以来かもしれない。
主人公のハンナには、隠しておきたい「秘密」がある。
勘のいい人なら、作者がそれとなく置いてくれているヒントでその秘密に気付くと思う。
その秘密はもう一人の主人公でもある語り手の「ぼく」が、
物語の真ん中あたりで、ようやく読者に教えてくれる。
ハンナの特徴に気付いていた人は、やはりなとにんまりするだけだが、
気付いていなかった読者は、ちょっと驚くだろう。
勘がいいことも考えもので、ちょっと驚けた方が、読書は楽しいと思う。
ドイツの知識人の多くがそうだったように、作者のシュリンクもナチの影を背負っている世代。
それが、ハンナという女性のもうひとつの「秘密」に投影される。
ぼくの前から忽然と姿を消したハンナは、偶然にも、法学生のぼくの前に姿を現す。
二人の愛は逢瀬を重ねていた頃とは、まったく違う形で、息を吹き返し、
しかもそのいとなみは、感嘆すべきある形で延々と繰り返されていく。
私が、もしかしてと思っていた結末に最後は落ち着いてしまうのだが、
ナチとホローコーストという構図のなかに、この物語を捉えても自由だし、
ぼくとハンナの半生という流れを、胸にしまい込むことも自由だと思う。
離れた国で、あの戦争から時間が経った平和な時代に生きている私でさえ、
ハンナの持っている二つの秘密に彼女の人生が翻弄されたことに、
まるでハンナを深く愛していたことがあるように、心を痛めるのである。
「彼女はあなたから手紙がいただけることを期待していたんです。彼女に何か送って 下さるのはあなただけでした。郵便物が配られるとき、彼女は『わたしへの手紙はあ りませんか?』と尋ねたものでした。彼女の言う『手紙』は、カセットの入っている 小包のことではありませんでした。どうしてあなたは彼女にお書きにならなかったん ですか?」 ぼくはまた沈黙した。話すことはできなかった。