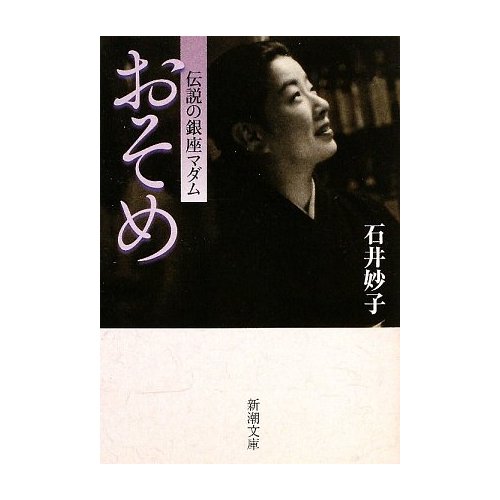
かつて銀座に川端康成、白洲次郎、小津安二郎らが集まる伝説のバーがあった。 その名は「おそめ」。 マダムは元祇園芸妓。小説のモデルとなり、並はずれた美貌と天真爛漫な人柄で、 またたく間に頂点へと駆け上るが――。 私生活ではひとりの男を愛し続けた一途な女。 ライバルとの葛藤など、さまざまな困難に巻き込まれながらも美しく生きた半生を描く。 隠れた昭和史としても読める一冊。
宣伝文句に「小説のモデルにもなった」とあるが、
かつて、銀座や北新地や祇園などのきれいなホステスさんたちを
「夜の蝶」と呼んだ時代があったが、
そのルーツをたどると、川口松太郎とおそめに行き着く。
京都に生まれて、新橋で芸者になり、祇園で芸妓になり、
京都と銀座に「おそめ」というバーを持ち、
昭和30年代に、東京と京都を飛行機を利用して頻繁に行き来した、
おそめこと上羽秀が、その主人公である。
「私生活ではひとりの男を愛し続けた」とあるが、
彼には和歌山に妻と3人の子がいたが、
おそめとは死ぬまで一緒で、ふたりは一子を授かっている。
和歌山に残していた3人の子どもの一番下の女の子は、名を純子といい、
著者の石井妙子は、京都のおそめと会いに、取材活動をはじめたのだが、
おそめの口からは「もう昔のことどすさかい・・・」などといなされ、
核心に触れることは適わなかったようで、
一時は、このノンフィクションの上梓をあきらめてかけていたと、あとがきで述べている。
しかし、取材がうまくいっていないのにもかかわらず、石井はおそめに会い続けた。
私はこの作品を読み進めるうちに、おそめという主人公や銀座や祇園の華やかさにではなく、
作者の石井に惹かれていくようになる。
なんとも魅力的なおそめのことを表現しようと、
資料をあたり、少しでもおそめとかかわりのあった人に会ってインタビューする。
5年もの歳月をかけて石井が調べたおびただしい資料の記録は巻末に紹介されているが、
誰と会ったという記録は書かれていない。(その理由は書かれている。)
私たちが何の気なしに読む1行に込められた、その確証を得るための取材は、
とてつもない作業を擁することがある。
1行1行には、それは誰に聞いたのかどうやって見つけ出したのかと思う箇所が随所にある。
おそめに関することを偶然発見しようとしても、いつまでたっても前に進まないだろう。
おそめ本人から思い出を聞き出して一冊の本にまとめることができたとしても、
主人公が生きてきた時代は書けなかったであろう。
各界の名だたる大物に慕われ続け、時代に愛され同時に蔑まされたおそめ。
「時代」は文字にはなくて、まさに行間に横たわっているものなのだが、
石井のこの作品にはそれがはっきり存在する。
糸をつむいで色を染めて機を織るような、
丹念な努力を要する取材の痕跡が楽しめる作品となっている。
ケータイ小説と称してさらーっと物語を書くのとは、まるで異次元の世界である、
石井は俊藤の娘、女優の純子に取材を敢行したのだろうか、
おそらく門前払いの憂き目に遭ったのではないかと、想像をするのだが、
残念ながら、どこにもそのことは書いてないので定かではない。
いずれにしろ、いくつかのあざやかなる「家族の肖像」に出会えた作品であった。